空はなぜ青いのか。
そして、夕焼けはなぜ赤いのか。
誰もが一度は感じたであろうこの疑問。
子どもに尋ねられて答えられなかった、という経験がある方もおられるでしょう。
子どもが分かるような説明は非常に難しいですが、解明されているその理由を紹介します。
空が青く見えるのはなぜ?‥レイリー散乱とは?
これを解明したのは、イギリスの物理学者J.W.レイリー卿(1842~1919)でした。
太陽光線が大気中の塵埃などにぶつかると、四方八方に散らばります。
これを散乱といいます。
太陽光線には様々な色の光が含まれていますが、その中でも特に青い光は散乱が起きやすく空が青く見えるのです(図1)。
これを、発見者の名にちなんで「レイリー散乱」といいます。
この現象は光の波長より小さい気体分子(酸素や窒素)に当たると起こります。
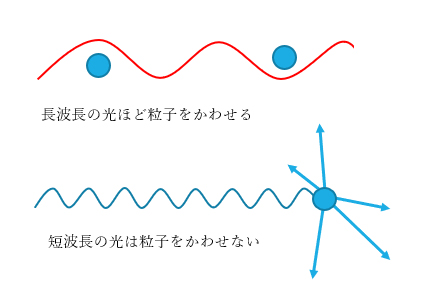
夕焼けが赤く見えるのはなぜ?
夕焼けが赤く見えるのは、太陽光が大気を通る距離に影響します。
昼間の太陽に比べて夕方(朝方)の太陽は地平線近くに傾くので、光が大気を通る距離が長くなります。
長い距離を進むうちに、散乱された青い光は弱まります。
散乱しにくい赤やオレンジの光だけが地上に届き、私たちはその色を見ることにより、夕焼けは赤く見えるのです(図2)。
この原理もJ.W.レイリー卿により解明され、「レイリー散乱」と呼ばれます。
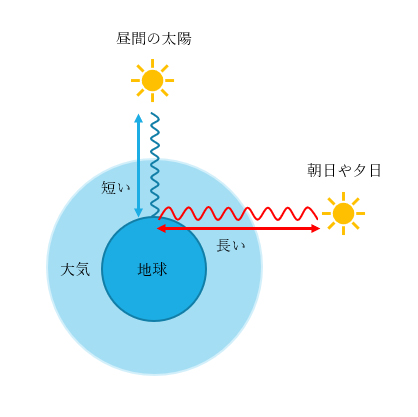
雲が白く見えるのはなぜ?‥ミー散乱とは?
太陽光が、光の波長より大きい水蒸気などの粒子に当たる時、すべての色の光が一様に散乱するので白く見えるのです(図3)。
グスタフ・ミーが解明したことにより、「ミー散乱」といいます。
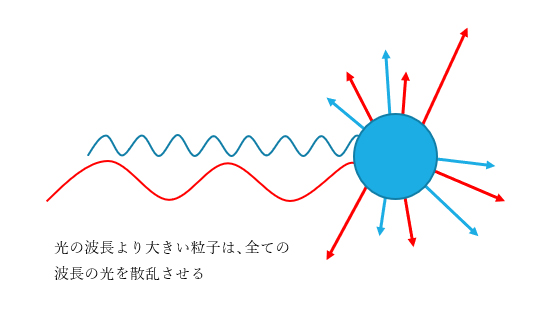
空の色と雲の陰
空を描く時に知っておくべきことがいくつかあります。
一番のポイントは太陽です。
太陽に向かうのか、太陽に背を向けるのかで空の色は違うのです。
また、それによって雲の見え方も違います。
太陽に向かっている場合、空はかがやきがあり、それが「青」と混じりあってすこしくすんだグレーに見えます。

逆に太陽を背にしている場合、「青」の彩度は高くなり、色みも豊かに見えます。

地表近くから天頂までの間では明るさも変化しており、地表に近い方が明るく見えます。
雲も太陽向かって見る場合と、その逆では、見え方が違います。
太陽に向かって雲を見ると、中央が暗くてエッジが明るくなっています。

太陽を背にして雲を見ると、上部が明るくなり、下部が暗くなります。
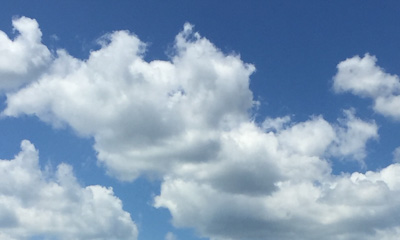
また、小さい雲はあまり白く見えません。
これは大きい雲に比べて、光を反射させる水蒸気の量が少ないからです。
普段、何気なく見ている空と雲ですが、注意して見るとずいぶん表情が違います。
ぜひ、じっくりと観察してみてください。
参考図書
最後に
普段何気なく目にしている空や雲ですが、注意深く観察するだけで、その色の違いに驚かれると思います。
何事に対しても、子どものような好奇心をもって臨めば、見えてくる世界も違ってくるということでしょうね。
遠近法、色彩、人体、構図などの講座ブログは、「絵画講座 / インデックス」として、まとめてありますので、ご活用いただければ幸いです。


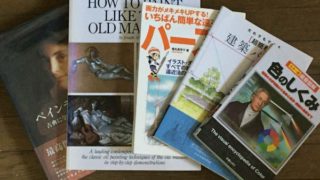




コメント