
生徒さんにもいろんなタイプの方がいらっしゃいます。
教室に臨む姿勢や性格など人それぞれです。
こちらの伝え方がよくなければ、怒らせたり傷つけることになってしまったり…。
そうならないように、生徒さんの言葉の裏側をくみ取ることが必要だったりもします。
ただ単に絵を描くために必要なことだけを話せばいい、というものでもありません。
絵画教室を始めてからすでに20年以上が過ぎましたが、教えることは本当に難しいと感じています。
この記事では、これまでの経験の中で、指導者として思っていることをまとめてみました。
指導は綱引きではない

教室に通って来られる方の目的はさまざまです。
上達を望んでいる方、単に一つの趣味として考えている方、友達と会ってお喋りをしたい方、この他にもいろいろな方がおられるのだと思います。
それほど上達を望んでいない方に対しては、楽しく過ごしていただければいいので、自由に描いていただきます。
友達とお喋りしたい方は、放っておけばいい。
ただ、邪魔になっていることに気が付いてない人もいますから、その時には注意します。
(大の大人を相手に、こんなことを注意しなければいけないのも、情けない話ですが…)
上達を望んでいる方の中にもさまざまおられます。
上手くなりたいとは言うものの、その意識をあまり感じない人。
あ~言えばこう言うタイプです。
次に、「上手くなりたい」としっかり伝わってくる人。
例えば、一言一句逃すまいと書き留めている人や、自宅でも描いてくる人などです。
上手いかどうかは関係ありません。
こういう方に対しては、どうすればより上手くなってもらえるか、思案しなければなりません。
普段の記録をもとに対策を考えます。
ある程度のレベルに達している人には、より難易度の高いことが要求できますから、新しい話をしたり負荷をかけたりしていきます。

要するに、指導者は生徒さんの意識レベルに応じた力でしか綱を引けないということです。
僕が習う立場であれば、本気で綱を引かせたいと思いますけどね。
「できなくてもいい」は嘘です!
生徒さんが課題に苦しんでいる時…、
「できなくてもいいですよ」
「分からなくてもいいですよ」
…などと言うことがあります。

はっきり言って、これはウソです。
教室でお話することは、「できない」よりは「できたほうがいい」ので、当然出来るようになって欲しいと思っています。
本当にできなくてもいいなら、わざわざ新しい技法や考え方を話したりしません。
あくまでも「今はできなくてもいい」ということですから、言葉の表面的な部分だけを鵜呑みにしないでいただきたいのです。
褒め言葉にご用心‥「褒める」と「おだてる」の違い

【褒めて伸ばす】という言葉があります。
「素敵ですね~」
「きれいに描けましたね!」
「元気がよくていい絵ですよ」
こういう安易な褒め言葉を聞かされることがあると思います。
いかにもそう思っているように、熱を込めて発せられている言葉です。
言われたほうも…
「嘘だ」
「どうせお世辞だ」
…とわかっているのでしょうが、やっぱり悪い気はしないようです。

僕自身の経験からいっても、褒め言葉の効果は抜群です。
こんな言葉でその気になってくれれば何よりです。
教室の雰囲気を悪くしたくないとか、辞めてもらいたくないということです。
こう考えると「褒める」のではなく、「おだてる」ことになってしまいます。
「褒める」と「おだてる」はよく似ていますが、相手に与える印象はぜんぜん違います。
ですから気持ちが伴っておらず具体性もありません。
■「褒める」ということは、相手が自分で気づいていない魅力や長所を伝えてあげることです。
場合によっては本人が短所だと思っていることも、 長所に変えることができます。
真摯に相手に向き合っていなければ言えないことです。
あなたが普段聞かされている言葉はどちらですか。
気持ちに嘘のある褒め言葉は単なるお世辞です。
言われて喜んでいる場合ではありません。
欠席者が多数の時こそ、学びのチャンス!

欠席者数の多い日があります。
こういう日は、講師を独占できるチャンスなんですから、せっかくの機会を逃す手はありません。
僕だったら、周りの目も気にすることはなくなるし、恥をしのんでいろんなことを聞きます。
しかし、みんながみんな僕のような性格ではなく、控えめな方はやっぱり控えめです。
そういう方には、こちらからアプローチして、疑問に感じていることを聞き出す絶好の機会でもあります。
特に、分からないからと言って、避けている内容に触れるには好都合です。

例えば遠近法は、難しいからと言って拒否反応を示す方は多いのですが、長く教室に通っていると断片的に知識が蓄積されている方は多いのです。
質問したいことは、たくさんあるはずです。
最初は様子を見ながら話しますが、少しずつペースは上がっていきます。
生徒さんからの質問もどんどん出てきます。
付きっきりで相手の表情を見ながら話せるので、理解できていないことを見逃すことはありません。
徹底的に詰めていくことができるので、おそらく、生徒さんの理解度は100パーセントです。
習う立場なら、欠席者が多い時はラッキーでしかないはずなんです。
教える側としては、休んでほしくないのが本音です。
「やる気あります!」‥生徒さんの声を素直に聞いてはいけない
僕自身、絵に関しては独学です。
しかも、始めたのは30才になる頃でした。
恥ずかしながら、つい最近までインターネットなんて全くできなかったので、描き方を紹介している動画も見たことがありませんでした。
ですから、実物を見て描くことだけを続けて今に至ります。
そうやって描き続けていると、たとえ分からないことがあっても、制作中に偶然答えが見つかることは多々あります。
絵が教えてくれるのです。
そんな風に勉強してきましたから、「まずはやってみる。そうすれば何か分かる」という考え方が、ベースにあります。

つまり、これは学習の基本です。
生徒さんにもこういう意識で臨んでほしいとは思いますが、わざわざ時間とお金を使って通っていただく「教室」ですから、必要最低限のことはお話しするべきだと思っています。
(ほとんど何も教えない教室もあるようですが…)
それ以上のことは、生徒さんの上達ぶりを見て判断します。
しかし、「やる気あります」とか「遠慮なく厳しく言ってください」なんていう生徒さんがいらしたら、つい嬉しくなっていろんなことを要求してしまいます。
課題も工夫して、時には厳しいことも言ってみたり。
(それも、かなり抑え気味に)
しかし、ふと気が付くと、かなりの温度差が生じている。
(あれっ? やる気あるんじゃなかったんですか?)
場合によっては怒り始める人もいらっしゃる。

最近、ようやく気付いたんです。
「やる気あります」という人に、本気で関わってはいけないと。
何かあると「いますぐ死んでやる~!」と口にする我が親のことを思いだします。
「じゃあ、いますぐ目の前で死んでみせて」と言ったこともありますが当然死なない。
安易に口にする人って、その程度なんです。
こちらの向き合い方を考えなければいけません。
描いて見せ、言って聞かせてさせるには、おだてたくらいじゃ人は動かん
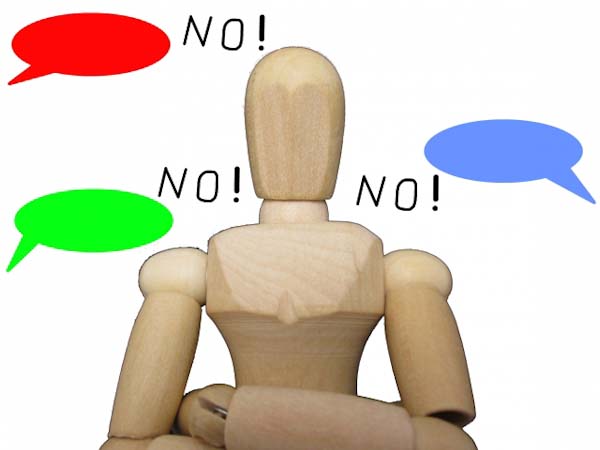
「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」
連合艦隊司令長官、山本五十六の名言です。
人材育成において、大切なことを説く言葉として知られています。
しかし、教室ではなかなかこの通りには実践できません。
描いて見せると、「あ~いうふうに描くのか~」という具合に、しっかり見てくれています。
説明もしっかりします。
「なるほど、なるほど」と、聞いてくれています。
しかし、させるとなると手強い。
「今日は、前の続きを描きますね」
「ムリです」
「家でゆっくり考えながらやります」
などの言い訳が並びます。
ホメオスタシスが起動するのです。
そこで、うまいこと言っておだてるのです。
おだてて、おだてて、課題のハードルも下げて、ようやくほんの少しやる気になってもらえる。
それでも、やらない人がいます。
やってもすぐに諦める。
描いて見せ、言って聞かせてさせるには、おだてたくらいじゃ人は動かんのです。
ホントに大変です。
ところで、この名言には、次のような続きがあります。
「話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。 やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。」
当時の日本でもこれですから、人を育てるのは楽じゃありません。
最後に
人に何かを教えるというのは、本当に難しいと実感します。
教室に通ってくる目的も違っていますし、同じ内容を同じように話しても、全員が理解してくれるとは限らないからです。
何年やっても答えは見つかりません。
遠近法、色彩、人体、構図などの講座ブログは、「絵画講座 / インデックス」として、まとめてありますので、ご活用いただければ幸いです。


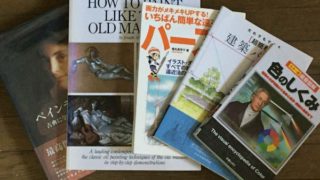




コメント